
社労士の難易度は高いと言われているけれど実際のところどうなんだろう。
こうした疑問に答えます。

そのため、社労士試験は高い難易度が要求されるものとされています。
本記事では、社労士試験の難易度について解説し、合格するための勉強法についても紹介していきます。
・本記事を書いている人

本記事の信頼性(この記事を書いている人)
・通信講座を利用して1年弱の勉強量で難関資格(弁理士)を突破。
・資格勉強の勉強法を公開してバズり1日に3万PV達成。
・資格勉強の勉強法を資格スクエアチャンネルに出演して公開。
・本記事の構成
1.社労士試験の難易度とは?
2.社労士試験の難易度を高める要因とは?
3.社労士試験に合格するための勉強法とは?
4.社労士試験に合格するためのポイントとは?
社労士試験の難易度とは?

| 社労士 | 税理士 | 司法書士 | 行政書士 | 宅建士 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 偏差値 | 65 | 75 | 76 | 63 | 57 |
社労士の難易度ランキングの偏差値は65です(参考:資格の取り方)。
他の士業の難易度ランキングの偏差値と比較すると、宅建の偏差値と比べると高いですが、税理士・司法書士などの偏差値よりは低く、行政書士の偏差値と同等です。
この理由は、税理士・司法書士などのいわゆる難関資格は、試験の形式に論述試験があるのに対し、社労士の場合、択一式の試験のみであることが考えられます。
論述試験の場合、答案の書き方を学ぶ必要があり、時間もかかりますが、択一式試験のみであることで試験にかける時間も短くなります。
このため、社労士の合格に必要な勉強時間も小さいです。
なお、行政書士試験の難易度はこちらをご参考に。
-

-
「行政書士試験の難易度と合格率」合格に必要な勉強法とポイント
続きを見る
社労士の難易度を勉強時間で見てみると!?
| 社労士 | 税理士 | 司法書士 | 行政書士 | 宅建士 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 勉強時間 | 1,000時間 | 2,500時間 | 3,000時間 | 800~1,000時間 | 250時間 |
勉強時間はフォーサイトなどの資格サイトのデータを参考にしています。
社労士の勉強時間は、1,000時間程度であり、1年がんばれば合格できる試験です。
-

-
社労士の勉強時間を800時間で最短合格するための独学勉強法
続きを見る
行政書士と同じくらいです。行政書士試験についてはこちらの記事をご参考に。
-

-
行政書士試験の勉強時間の使い方!合格に必要な勉強時間とは?
続きを見る
一方、税理士・司法書士などの難関資格の場合、2~3年がんばる必要があります。
難関資格といわれていますが、1年の勉強量で合格できる試験であることがわかります。
社労士の合格率はどれくらい!?
| 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 合格率 | 6.8% | 6.3% | 6.6% | 6.4% | 7.9% |
社労士のここ最近の合格率です。(参考:厚生労働省のデータ)
現在は、6~7%ほどの合格率で安定しています。
このデータを見てみると、やはり社労士は難しい試験だと思われるかもしれません。
しかし、社会人であっても1年頑張れば合格できる試験であり、それほど難しくないといえます。
理由を以下に解説していきます。
社労士の難易度が高くないといえる理由
社労士の難易度が高くないといえる理由は以下のとおりです。
- ①試験回数が1回しかない。
- ②しかも選択式。論述と口述なし
- ③試験範囲は広いと見えて全ての試験科目は関連性あふかり。
- ④勉強法は確立されている。
正直言って800時間の勉強時間が与えられれば筆者は受かる自信あります。(偉そうですみません…)
以下理由を解説していきます。
①試験回数が1回しかないことと択一式のみ
士業の資格では珍しく社労士試験は試験回数1回だけ。しかも択一式のみです。
つまり、論述試験と口述試験がありません。この負担はとても大きく、これがないだけで相当楽です。
論述試験がある場合、答案の書き方、つまり文章力を鍛える必要があります。文章力を鍛えることは独学では難しいですし、答案がこれでよいのか分からないこともあり、けっこう大変です。
これに対し、社労士の場合には、文章力は鍛える必要はありません。とても楽に思います。
②試験範囲は広いと見えて全ての試験科目は関連性あり
また、社労士の試験範囲は一見広そうに思えますが全ての試験科目に関連性があります。
- 1.労働基準法
- ※労働者を守るための法律です。年次有給休暇・労働条件・賃金・就業規則を学びます。
- 2.労働安全衛生法
- ※作業現場での危険や健康障害から守るための法律です。
- 3.労働者災害補償保険法
- ※いわゆる労災保険に関る法律です。
- 4.雇用保険法
- ※失業保険、高年齢者雇用継続給付、育児休業給付などを定めた法律です。
- 5.労働保険徴収法
- ※労働者災害補償保険と雇用保険を維持するために事業主と労働者から保険料が徴収されます。この保険料の徴収の仕組みに関する法律です。
- 6.労務管理その他の労働に関する一般常識
- ※上記以外の法律の労働者に関する法律全般についての一般常識問題です。
- 7.健康保険法
- ※医療費を国が援助する制度に関する法律です。
- 8.国民年金法
- ※自営業者などが対象の国民年金に関する法律です。
- 9.厚生年金保険法
- ※サラリーマンなどが対象の厚生年金に関する法律です。
- 10.社会保険に関する一般常識
- ※上記の社会保険以外の法律に関する様々な法律から出題されます。
いずれも社会保険・年金に関する科目であり、広すぎるように見えていずれも「労働・保険・年金」のひとくくりでまとめることができます。
実質3科目ぐらいであり、意外と科目数は多そうで多くはないと思います。
③勉強法は確立されている。
最後にこうした選択肢問題のみの試験の場合、正しい勉強法は確立していると思います。
筆者の勉強法が必ずしも正しいとは限りませんが、あとで紹介します。
社労士試験の難易度を高める要因とは?


- 試験範囲が広い
- 一年に一度しか受験できない
- 合格率が数パーセントと低い
社労士試験出題範囲は広く、社会保険、労働法、労働保険、労働基準法、労働安全衛生法など幅広い分野の知識が必要となってきます。
このため、社会人では、幅広い範囲を勉強する時間がなく不合格になりがちであり、結果として合格率が数%と低いものであると考えられます。
ただし、社労士試験は、論述試験がありません。
つまり、文章力はそこまで問われない試験となります。
このため、確かに社労士試験は難しいと感じる方もいると思われますが、文章のセンス・文章力は問われないため、
しっかりとコツコツ勉強して知識をインプットすれば合格できる試験といえるでしょう。
では続いて社労士試験の勉強法について解説していきます。
社労士試験に合格するための勉強法
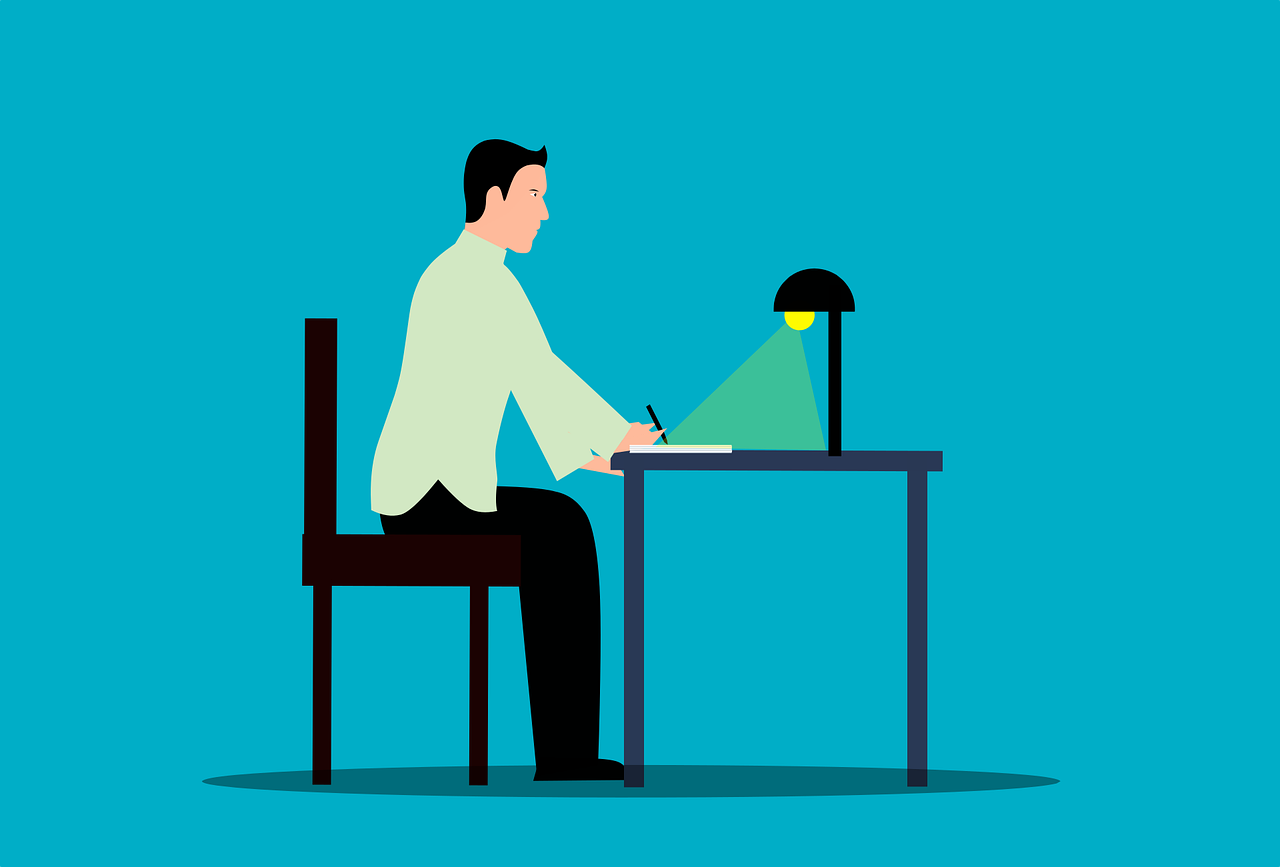
具体的な勉強法は以下の記事で詳しく解説しているので、ここでは概要だけにとどめておきます。
-

-
資格勉強の勉強法のやり方と一発合格するコツを解説【難関資格向け】
続きを見る
- 1.通信講座の入門・基礎動画を全部流し見する
- 2.一単元ごとに見直し、あわせて過去問を解いていく
- 3.過去問でできなかったところを重点的に繰り返す
- 4.2と3を繰り返す
以下ではポイントを解説します。
アウトプットは過去問だけでOKです。
20年分以上はやりこみましょう。
最初に入門・基礎動画を全部流し見することで全体を把握し、一単元ごとに勉強する上で敷居を低くしています。
一単元ごとに見終わったら、その都度に過去問を解いていきます。
インプットとアウトプットをバランスよくおこなっていきます。
ここで、わからないところがあっても次へすすめていきます。
次へ次へとすすめていくと、わからないところもわかっていくようになります。
これを1年を目標に継続していきます。
筆者は社労士とは異なりますが、弁理士の試験勉強でこの方法で合格しています。
弁理士も社労士も法律の資格という点では同じであり、この勉強方法は社労士試験にもあてはまりうると考えています。
もしあなたが、勉強時間をより確保できるのなら、半年間でもいけるでしょう。
この勉強法は独学でテキストを購入して対応できますが、通信講座を使うとさらに効率的です。
というのも、動画だとあなたが見たいときに好きなタイミングで見られるためやりやすいからです。
-

-
【2023年最新】社労士通信講座のおすすめと比較は?失敗しない選び方も解説
続きを見る
社労士試験の代表的な通信講座を比較してみると以下のとおりとなります。
| フォーサイト | アガルート | スタディング | ユーキャン |
|
|---|---|---|---|---|
| 価格 | ¥78,800~ | ¥87,780~ *2023年合格目標の場合は30%OFFで61,446円 |
¥46,800~ | ¥79,000 |
| 講座内容 | ・フルカラー製本 ・講義動画 (PC・スマホ・タブレットで視聴可能) |
・フルカラー製本 ・講義動画 |
・WEBテキスト ・冊子版つきであればさらに+28,600円 ・スマホ1つで講義動画 |
・フルカラー製本 ・講義動画 |
| サポート | ・合格者スタッフが質問回答(上限あり。) ・条件付きで不合格の場合全額返金保証制度あり。 |
・質問無制限OK ・オプションで「定期カウンセリング」制度あり。 ・条件付きで合格者全額返金制度あり。 |
・質問はチケット制(有料) ・条件付きで合格したらお祝金10,000円 |
・質問OK(1日3問まで。) ・添削あり(11回) |
| 合格実績 | 22.4% (2022年度) |
27.37% (2022年度) |
合格者の声74名(2022年度) | 10年間の合格者累計2,100名突破 |
| 申込み | こちらから | こちらから | こちらから | こちらから |
| 評判・口コミの記事 |
※価格・合格実績は変動することがありますので上記の各通信講座のサイトで確認してください。
社労士試験に合格するためのポイント

社労士試験で失敗しないために重要なポイントとしては以下のとおりです。
1。あらかじめ出題範囲を把握しておくこと
2.過去問をしっかりとこなすこと
3.試験前に自己分析をすること
4.本番前はしっかりと体調を整えること
まず、試験勉強の前に出題範囲をしっかりと把握しておき、スケジューリングをたてましょう。
試験直前で全ての範囲まで勉強できなかった、という過ちを回避できます。
そして、試験本番までゆとりをもって勉強をすることをおすすめします。
また、問題集は過去問をしっかりとこなしましょう。
筆者もまた、別資格ですが予備校が独自で作成した問題集などを使わず過去問を何度も繰り返し勉強しました。
その結果が合格にいたっていると考えています。
過去問を繰り返し解答することで傾向や時間配分・要領などが見えてきます。
さらに、試験前に自分の不足している分野や苦手分野はどこか分析しておきましょう。
最後に、当たり前ですが試験本番の1週間くらい前までは無理をせず体調をととのえて万全の態勢で試験にのぞみましょう。
社労士の難易度のまとめ

| 社労士 | 税理士 | 司法書士 | 行政書士 | 宅建士 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 偏差値 | 65 | 75 | 76 | 63 | 57 |
社労士試験は勉強のコツを知ってすぐにとりかかることをおすすめします。
勉強には通信講座がおすすめです。
通信講座のおすすめはこちらの記事を参考にしてみてください。
-

-
【2023年最新】社労士通信講座のおすすめと比較は?失敗しない選び方も解説
続きを見る
社労士試験の代表的な通信講座を比較してみると以下のとおりとなります。
| フォーサイト | アガルート | スタディング | ユーキャン |
|
|---|---|---|---|---|
| 価格 | ¥78,800~ | ¥87,780~ *2023年合格目標の場合は30%OFFで61,446円 |
¥46,800~ | ¥79,000 |
| 講座内容 | ・フルカラー製本 ・講義動画 (PC・スマホ・タブレットで視聴可能) |
・フルカラー製本 ・講義動画 |
・WEBテキスト ・冊子版つきであればさらに+28,600円 ・スマホ1つで講義動画 |
・フルカラー製本 ・講義動画 |
| サポート | ・合格者スタッフが質問回答(上限あり。) ・条件付きで不合格の場合全額返金保証制度あり。 |
・質問無制限OK ・オプションで「定期カウンセリング」制度あり。 ・条件付きで合格者全額返金制度あり。 |
・質問はチケット制(有料) ・条件付きで合格したらお祝金10,000円 |
・質問OK(1日3問まで。) ・添削あり(11回) |
| 合格実績 | 22.4% (2022年度) |
27.37% (2022年度) |
合格者の声74名(2022年度) | 10年間の合格者累計2,100名突破 |
| 申込み | こちらから | こちらから | こちらから | こちらから |
| 評判・口コミの記事 |
※価格・合格実績は変動することがありますので上記の各通信講座のサイトで確認してください。